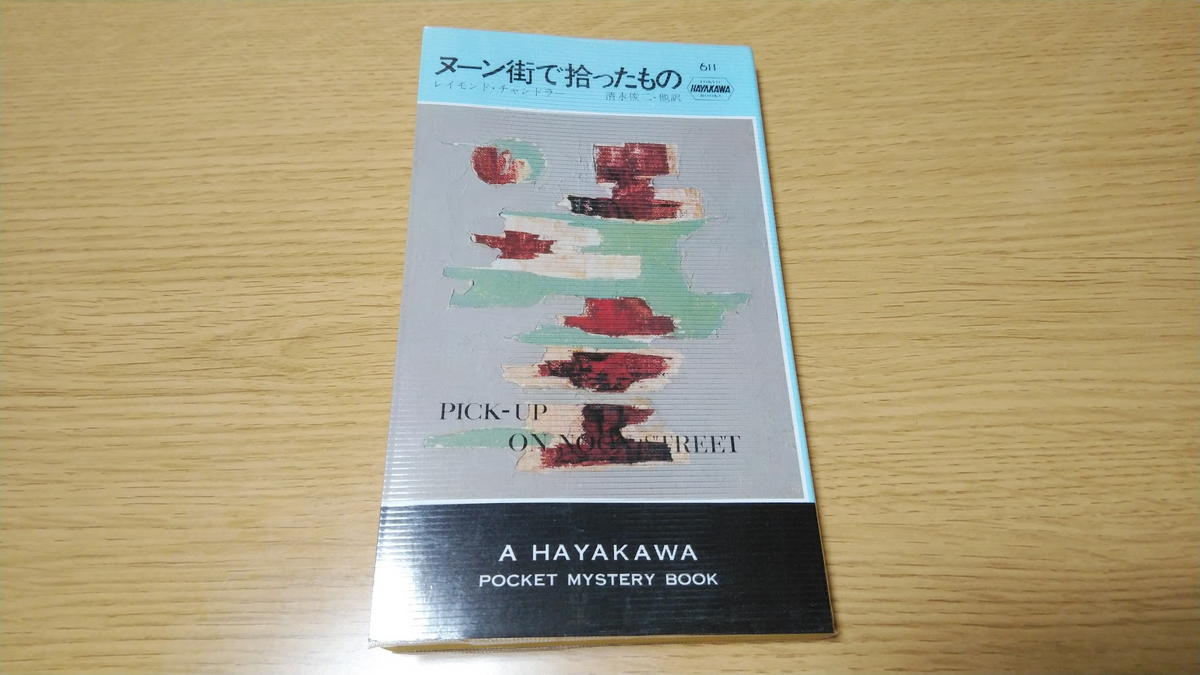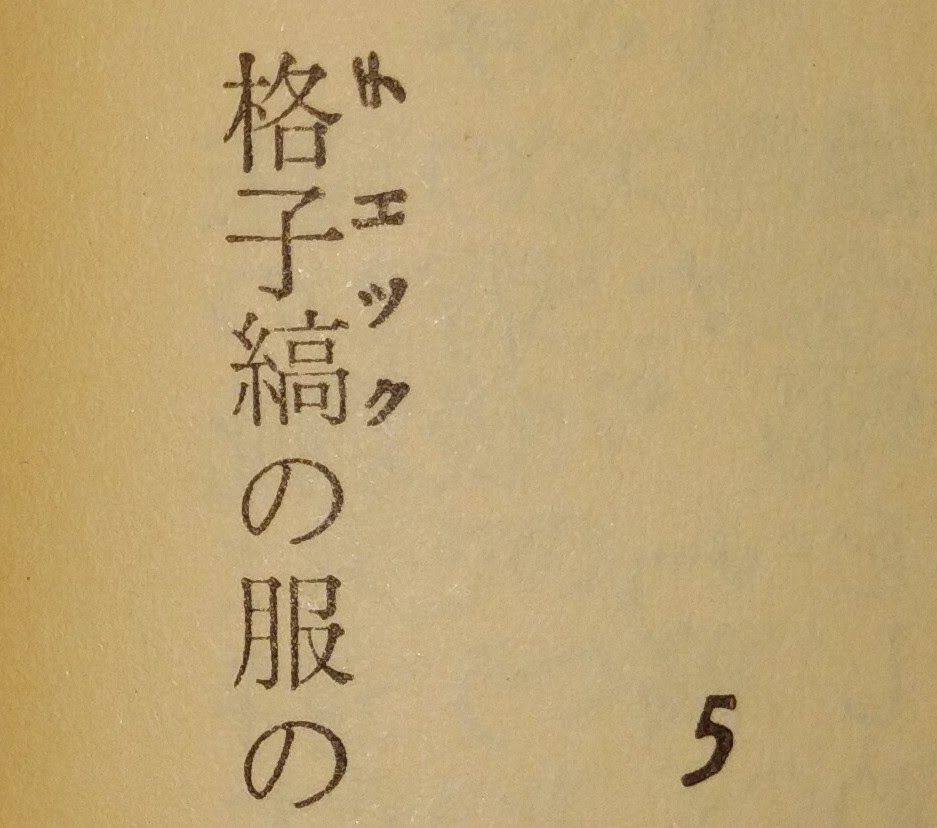教習所に行った。
持参したおにぎりがリュックの中で破裂して、教本に米粒が付いてしまった。
水筒のフタが開いていて教科書に麦茶のシミができるというのはあるあるだが、教科書に米粒を付けているのは裸の大将くらいのものだろう。
おにぎり自体は見た目には汚れていなかったのが不幸中の幸いだった。
午前の教習を終え、カフェスペースで件のおにぎりを頬張る。
いつもは車に関するビデオをエンドレスに垂れ流しているテレビが、今日は野球の中継を流している。
常に無音のテレビなのでしばらく気付かなかったのだが、教官や高齢者講習を受けに来たご老人がやたらとやって来るので何かと思っていたら、野球をやっていたのだ。
ただ壁を見ながらおにぎりを食べるのもヒマなので、チラチラとテレビに視線を投げる。
おかげで日本の勝利の瞬間を見ることができた。ラッキー。
その十数秒後、私の後ろのテーブルに座っていた男が「え、ウソ!よっしゃ!」と、にわかに騒ぎ出した。
どうやら彼は自分のスマホで中継を見ていたようで、時差で日本の勝利を知ったらしい。
人目を憚らずにガッツポーズをして、イスをガタガタいわす男。ちょっと落ち着け。
私は彼のスマホを見たわけではないが、周りの状況から彼が野球を見ているのだと思った。
彼が受験の結果や賭け事の結果を見ていたとしても、周りの人間には野球を見ているとしか思われない。
なんだか変な気分だった。なんかのトリックに使えないかな。
これまでの人生で、私は何度ガッツポーズをしたのだろう。
数回しかしていない気もするし、意識していないだけで何度もしている気もする。
ただ、明確に記憶しているガッツポーズもある。
小学五年のある日、私たちの学年は体育館に招集された。
間近に迫るキャンプに向け、カレー作りのグループを決めるのだ。
私たちの学年は三クラス。
まず各クラス内で小さなグループを作り、くじで小グループを三から四つ組み合わせて大きなグループを作るという方法だった。
つまり、運が良ければ見知ったクラスメイトだけで大グループを構成できるのだ。
まあ、この学年も五年目だし、知らない顔が集まるなんてこともないだろう。
ところが、くじの結果はそう甘くなかった。
よりによって私たちは、交流が薄い他クラスのグループと組むことになってしまったのだ。
私たちは絶望した。向こうも絶望していたと思う。
しかし、天は我々を見放してはいなかったのだ。
「くじにミスがあったのでやり直します」という天声が聞こえてきた。
やり直しといっても全てではなく、直前にくじを引いた私のクラスだけだった。
知らない人が集まったグループから私たちだけが脱出できる可能性が出てきたのだ。
この知らせに私はガッツポーズをした。
私のクラスの他の小グループたちも先の結果には不服だったとみえて、皆大喜びをしていた。
「オイ!」
突然、私の担任が怒鳴った。
「喜ぶな、失礼だろ」
その瞬間、私を含めたクラスメイトは全員もれなく「しゅん・・・」となった。
そうだ、私たちはとんでもなく失礼な振る舞いをしてしまったのだ。
恥ずかしい、恥ずかしかった。
バレーボールのポールを刺す穴に入りたいほど恥ずかしかった。
しかも、くじの引き直しの結果、私たちは先ほどと同じグループに入ることになった。
因果応報だ。
人生で一番気まずい思いをしつつ仲間とともに詫びると、「こうなる気がしたよ」というなんともなコメントが返ってきた。
この出来事以来、私は感情を露わにして喜ぶことをしなくなった。
しっかり考えてから静かに喜ぶようになった。
大人になると、大々的に喜ぶ出来事も減ってくる。
スポーツって、良いですね。
今週の読了本
若竹七海さんの『死んでも治らない 大道寺圭の事件簿』

元警察官・大道寺圭は、一冊の本を書いた。警官時代に出会ったおバカな犯罪者たちのエピソードを綴ったもので、題して『死んでも治らない』。それが呼び水になり、さらなるまぬけな犯罪者たちからつきまとわれて・・・・・・。大道寺は数々の珍事件・怪事件に巻き込まれてゆく。
ブラックな笑いとほろ苦い後味。深い余韻を残す、コージー・ハードボイルドの逸品!
-裏表紙より引用
講演後にチンピラに拉致される「死んでも治らない」、顔見知りの小悪党に娘探しを依頼される「猿には向かない職業」、読者から届く推理小説の添削依頼の手紙が思わぬ事態を招く「殺しても死なない」、死んだジャーナリストの遺稿を引き継ぐことになった大道寺が噴火間近の山で奮闘する「転落と崩壊」、葉崎市での講演直前に海上で監禁されてしまう「泥棒の逆恨み」といった大道寺の不運ぶりと鋭さが味わえる五つの短編。
それに加え、「大道寺圭最後の事件」というフリーライター殺しの捜査の模様が分割されて各話の前後に挿入されている。なぜ大道寺は警察を辞めたのか。物語を読み進めていくと、事件がどんどん繋がっていくスーパー・オムニバス・ミステリー。まさに因果。
葉村晶シリーズに雰囲気が近く、とても面白かった。
解説によれば、葉崎市シリーズのみならず『ぼくのミステリな日常』や『スクランブル』とも関連しているらしい。
読む順番をまた間違えた。
『ミステリアス・ジャム・セッション』も買おうかな。
<了>